東洋大学での除籍と卒業、この二つの言葉が持つ重みは、想像以上に違うものなんです。私も学生時代を思い出して、その違いを改めて考えてみると、胸に迫るものがありますね。まるで、同じキャンパスを歩いていたはずの道が、ある日突然、天国と地獄に分かれてしまうような、そんな劇的な違いがあるんですよ。
学籍を巡る運命の分かれ道
まず、「卒業」というのは、本当に輝かしい響きを持っていますよね。大学で必死に学んだ成果として、必要な単位を取り終え、晴れて学士の学位を授与される。これは、努力が実を結んだ証であり、新しい人生の扉を開く、まさに希望に満ちた瞬間です。卒業式で友人たちと肩を組み、喜びを分かち合ったあの時の感動は、一生忘れられない宝物になるはずです。私の友人も、卒業証書を手にした時の顔は、それまでの苦労が報われた達成感に満ち溢れていました。彼を見て、私も心から「本当によく頑張ったね」と、ねぎらいの気持ちでいっぱいになったものです。卒業は、将来の選択肢を大きく広げてくれます。就職活動においても、多くの企業が「大卒以上」という条件を掲げているように、学士の肩書きは、社会へのパスポートのような役割を果たすことが多いんです。専門知識の習得はもちろん、大学生活で培われる自主性や問題解決能力、多様な人との出会いによる人脈形成など、そのメリットは計り知れません。
一方で、「除籍」という言葉には、正直なところ、冷たい響きを感じてしまいます。これは、学生が自らの意思で大学を去る「退学」や「中退」とは一線を画します。除籍は、大学側が学生の学籍を強制的に抹消する、いわば「処分」の色合いが濃いんです。学費の未納が続いたり、定められた在籍年数(東洋大学では8年という期間があるそうですね)を超えてしまったり、あるいは大学の規則に著しく反する行為があったりする場合に、この重い決断が下されることがあります。
例えば、私の大学時代の知り合いで、病気で長期入院を余儀なくされ、復学の申請が遅れてしまった結果、やむなく除籍になった人がいました。彼の悲痛な顔は今でも忘れられません。彼の場合は、悪意があったわけではなく、不測の事態だったのですが、それでも除籍という現実が彼を追い詰めていました。除籍は、大学に「在籍していた」という事実は残るものの、大学側から学籍を剥奪されたという事実は、その後の人生に少なからず影響を与える可能性があります。特に就職活動においては、「なぜ除籍になったのか」という理由を深く問われることもあり、説明に苦慮する場面が出てくるかもしれません。
未来を拓く、その道のり
卒業と除籍、この二つの間には、まさに天と地ほどの差があると言っても過言ではないでしょう。卒業は、努力と成長の証であり、未来への明るい展望を抱かせてくれるものです。大学で得た知識や経験、そして仲間との絆は、卒業後の人生においてかけがえのない財産となるはずです。
それに対して、除籍は、たとえやむを得ない事情があったとしても、その事実が重くのしかかることがあります。もちろん、除籍になったからといって、人生が終わるわけではありません。そこから再起を図り、新たな道を見つける人もたくさんいます。大切なのは、どんな状況に置かれても、諦めずに前を向くこと。しかし、もし可能であれば、除籍という結果だけは避けたいと、心から願うばかりです。大学生活は、決して平坦な道のりばかりではありませんが、困難を乗り越え、卒業というゴールテープを切った時の喜びは、何物にも代えがたいものです。どうか、皆さんがその喜びを味わえるよう、心から応援しています。

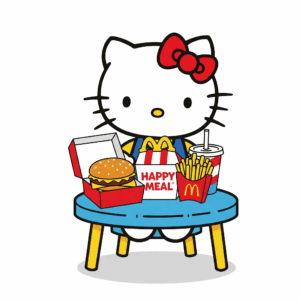






コメント